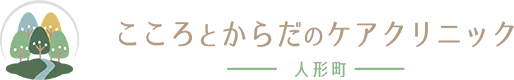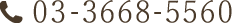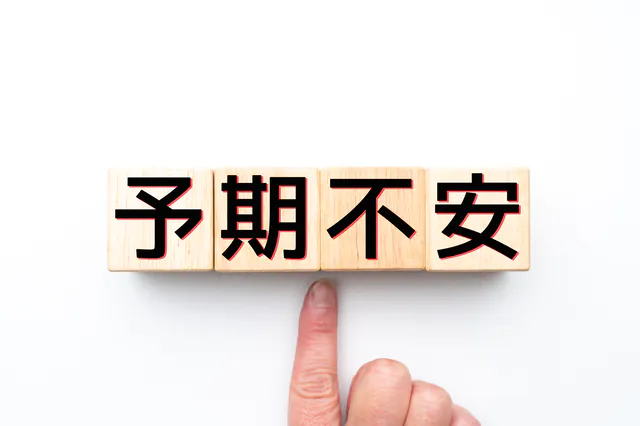 ■予期不安とは?
■予期不安とは?
予期不安とは、不安障害やパニック障害の患者さんに見られる症状の一つで、『また発作が起きたらどうしよう』『次の発作はもっと激しいのではないか』『発作が起きたら命に関わるのではないか』といった強い不安を指します。これは発作を繰り返すうちに、発作が起きていない時でもその可能性を恐れ、不安を感じる状態です。
予期不安は、不安障害やパニック障害が改善した後でも残ることがあり、適切な対応が必要です。周囲から見ると『大丈夫』『気にしすぎ』と思われるかもしれませんが、患者さんは深刻に悩み、苦しんでいるため、専門家による治療が重要です。また、家族や周囲の方も正しいサポート方法を学ぶことが求められます。
■予期不安の症状
-
- また発作が起きるのではないか
- 発作が起きたらどうしよう
- 次に発作が起きたらもっと激しいのではないか
- 次に発作が起きたら死んでしまうのではないか
- (車の運転中に)事故を起こしてしまうのではないか
- (発作を起こした場所から)逃げ出せないのではないか
- 人前で恥をかく、失敗するのではないか
など
予期不安の強さ(重症度)
軽症ー 多少の不安を感じるものの、必要なところには外出できる。中等症ー ひとりでの外出は難しいなど、行動に制限がある。
重症ー付き添い無しでは外出できず、ほどんど家に引きこもった状態である。
■予期不安が及ぼす影響
日常生活への影響
予期不安は、まだ起こっていない出来事への過剰な心配や恐怖を伴うため、日常生活に大きな影響を与えることがあります。例えば、仕事や学校に行くことが難しくなったり、人間関係に支障をきたすこともあります。また、予定や約束を避けるようになり、社会的な孤立感が深まるケースも少なくありません。
身体への影響
予期不安は精神的な影響だけでなく、身体にも影響を及ぼすことがあります。例えば、動悸、息切れ、めまい、胃腸の不調などが現れることがあります。これらの身体症状は、予期不安をさらに悪化させる悪循環を引き起こす可能性があります。
予期不安のある方の考え方(捉え方)
不安障害やパニック障害によるパニック発作を経験し、『また発作が起きたらどうしよう』という恐怖に襲われると、人はその状況から逃げ出したくなる傾向があります。また、その場や場面を避け続けるうちに、そこを『発作が起きる場所・状況』と過剰に意識してしまう傾向があるとされています。このようにして、『あそこに行くと発作が起きる』『あれをすると発作が起きるかもしれない』といった負のスパイラルに陥り、自分自身の行動範囲や活動の幅をどんどん狭めてしまいます。
さらに、患者さん自身がそのような自分を否定的に捉え、『自分はダメな人間だ』と自己評価を下げてしまうことも少なくありません。このことが、うつ病や適応障害につながるとされています。
■予期不安の治療
予期不安が見られる場合には、不安障害やパニック障害の治療法を基に、薬物療法や心理療法が行われます。
薬物療法では、抗うつ薬であるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)や、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬が主に使用されます。SSRIは効果が現れるまでに1~2週間程度かかるため、即効性を求める際にはベンゾジアゼピン系抗不安薬が使用されることが一般的です。また、ベンゾジアゼピン系抗不安薬は、適切に使用すれば高い効果が期待できる薬ですが、誤った使用方法により離脱症状が現れることがあります。そのため、必ず医師の指示に従って使用することが重要です。
精神科デイケアについて
予期不安の改善には、精神科デイケアを活用して生活リズムを整えながら、少しずつ外出できる環境を整え、社会参加を促すことが効果的とされています。当クリニックでは、精神科デイケアが有効と考えられる患者さんに対して、近隣の医療機関をご紹介しております。お気軽にご相談ください。
予期不安の症状を和らげる方法
予期不安を和らげるには、心と体のリラックスを促す方法が効果的です。まず、深呼吸や腹式呼吸を取り入れることで、体の緊張をほぐし、不安を軽減できます。また、瞑想やマインドフルネスを実践し、現在に集中する習慣をつけることも有効です。適度な運動はストレスホルモンを減らし、心の安定に繋がります。さらに、信頼できる人に話を聞いてもらうことで、気持ちが整理されることもあります。症状が重い場合は、専門医に相談し、認知行動療法や必要に応じた薬物療法を検討しましょう。自分に合った方法を取り入れ、日常的にケアを行うことが大切です。
監修:こころとからだのケアクリニック人形町 院長 益子 雅笛(ますこ みやび)