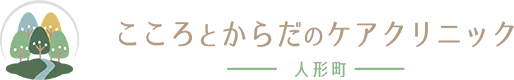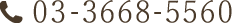■自律神経の乱れとはどんな症状?
■自律神経の乱れとはどんな症状?
自律神経とは、医学的に交感神経と副交感神経を合わせたものを指し、いずれも自分の意志で制御することはできません。自律神経は内臓に広く分布し、これがバランスよく働くことで、心臓が状況に応じて脈拍を速くしたり、遅くしたりすることが可能になります。このため、意志の力で心臓を止めることは不可能です。自律神経は、身体を活発にさせる役割を持つ交感神経と、休息を促す副交感神経がうまく調和することで、全身の器官をコントロールし、必要なタイミングで必要な働きをサポートする一方で、無理をしすぎて器官が損傷しないよう保護する役割を担っています。
自律神経のバランスが崩れると、緊張が高まり、吐き気、多汗、頭痛、肩こり、動悸、手足のしびれ、不整脈、めまい、不眠(眠れない・目が覚めやすい)、不安感など、さまざまな症状が現れるようになります。また、精神的な症状だけでなく、胃酸の過剰分泌による胸焼けや胃痛、腹痛、便秘、下痢、過敏性腸症候群などの消化器症状を引き起こすこともあります。これらの一連の症状が現れる状態を、自律神経の乱れと考えます。
自律神経を整えるにはどうすればいいの?
自律神経を整えるには、生活リズムの安定、バランスの良い食生活、適度な運動、ストレスを溜めない工夫(上手に発散する方法を見つける)、そして自分自身をよく知ること。この5つを意識することが大切だとされています
生活リズム
自律神経は、身体を活発にする交感神経と、休息を促す副交感神経がバランスよく働くことで、全身の機能を調整しています。しかし、睡眠不足や昼夜逆転の生活、偏った食事などで生活リズムが乱れると、交感神経が優位になる時間が増え、バランスが崩れやすくなります。同様に、夜遅くまでスマホなどでブルーライトを浴び続けることも脳と体の休息を妨げる原因になります。働く時間と休む時間の両方をしっかり確保することを意識してみましょう。
食生活
生活リズムの整え方と関連しますが、偏食や過食は自律神経を乱す原因になりかねません。そのため、1日3食を可能な限り決まった時間に摂り、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。以下に、自律神経を整えるために特におすすめの食品を紹介しますので、日々の食事の参考にしてみてください。
ビタミンB群
魚介類や卵、海苔、レバー、赤身肉に多く含まれるビタミンB12は、自律神経の働きをサポートする成分とされています。また、ほうれん草、落花生、豚肉に含まれるビタミンB1は、脳の糖質代謝を促す効果が期待されます。これらのビタミンB群を意識的に食事に取り入れるようにしましょう。
ビタミンC
パプリカ、レモン、ブロッコリーに豊富なビタミンCは、ビタミンEの働きを助けるとされています。そのため、ビタミンEとともに、日々の食事に積極的に取り入れることが大切です。
ビタミンE
マグロ、ウナギ、ナッツ類、カボチャに多く含まれるビタミンEは、抗酸化物質として知られています。この抗酸化物質は、交感神経が優位な状態で増加する活性酸素を還元することで、副交感神経の働きを促すとされています。
トリプトファン
乳製品、大豆製品、バナナ、雑穀、鶏むね肉に豊富なトリプトファンは、リラックス効果が期待される成分です。この成分は、ストレスを抑える作用を持つセロトニンという脳内神経伝達物質の材料となります。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。特に食生活が偏りがちな場合には、普段の食事でトリプトファンが十分に摂れているか確認してみましょう。
カルシウム
切り干し大根、小松菜、豆腐、乳製品、小魚に豊富なカルシウムには、交感神経の働きを抑える効果があるとされています。また、不安やイライラといった自律神経の乱れに伴う症状を和らげる働きも期待されています。
軽い運動
自律神経のバランスを整えるためには、ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、無理なく続けられる軽い運動を日常に取り入れることが大切です。また、腹式呼吸や深呼吸も効果的とされています。交感神経をリラックスさせ、副交感神経を活発にすることがポイントです。無理のない範囲で少しずつ始めてみましょう。
ストレスを溜めない(上手く発散する)
自律神経の乱れを防ぐためには、ストレスを溜めないことが理想ですが、仕事や育児、家事などの場面でストレスを全く抱えない生活を送るのは難しいのが現実です。そのため、ストレスとどのように向き合い、上手に発散するかを工夫することで、より快適に生活できるでしょう。自律神経を整えるには、個々に合った方法を見つけることが大切です。たとえば、読書や音楽を楽しむことが効果的な人もいれば、アロマテラピーが適している人もいます。運動と同じく、副交感神経を優位にする活動を取り入れることがポイントです。
自分をよく知る
自律神経を整えるためには、日頃から自分の状態を少し意識する習慣を持つことが大切です。たとえば、日記に体調の変化を記録してみることや、意識的に腹式呼吸を取り入れることが挙げられます。これらは、自分の体調を振り返るきっかけとなり、自律神経の乱れに気付く手助けになるでしょう。
■自律神経の乱れに受診や薬は必要?
自律神経の乱れが気になる場合、受診や薬による治療が必要か迷う方も多いかもしれませんが以下の対応を検討することが重要になります。
- 症状を我慢せず医療機関を受診する
- 自律神経を整える薬や漢方薬を活用する
症状を我慢せず医療機関で相談しましょう
自律神経の乱れによる症状が気になる場合は、まず医療機関で専門家に相談することが大切です。我慢を続けると、症状が悪化したり日常生活に支障をきたしたりすることがあります。
受診先がわからない場合は、特に気になる症状に合わせて医療機関を選ぶと良いでしょう。
例えば:
- 腹痛や吐き気などの身体的な症状がある場合は、内科や消化器系の病院が適切です。
- 不眠やイライラ、不安感などの精神的な不調がある場合は、心療内科や精神科を検討してください。
専門医による診察を受けることで、自律神経の乱れの原因や適切な治療法が明確になります。自己判断で放置するよりも早期に対応することで、症状が改善しやすくなります。
自律神経を整えるための薬や漢方薬
自律神経の乱れを改善するためには、西洋医学の薬と東洋医学の漢方薬が利用されることがあります。それぞれの特性を理解した上で、医師と相談しながら最適な方法を選ぶことが重要です。
西洋医学の薬
西洋医学では、自律神経の乱れそのものを直接治療する薬はありませんが、症状を軽減するための薬が処方されます。
- 睡眠薬:睡眠を促進し、休息をしっかり取ることで自律神経の回復を助けます。
- 抗うつ薬:精神的な負担を軽減し、気分の安定を図ります。
- 抗不安薬:不安や緊張を緩和し、リラックスを促します。
これらの薬は、脳内の神経伝達物質に作用することで、ストレスや不安を和らげる効果があります。ただし、副作用の可能性もあるため、医師の指示に従い適切に使用することが大切です。
東洋医学の漢方薬
東洋医学では、漢方薬を用いて体質を根本から改善するアプローチが取られます。
診察では「四診法」と呼ばれる方法を用い、脈や舌の状態を観察しながら患者さんの体質や症状に合った治療法を決定します。
- 例:**加味帰脾湯(カミキヒトウ)**は、不安や緊張感を緩和し、心身のバランスを整える効果が期待されます。
漢方薬は、自然由来の成分を使用しているため、体に優しく長期的な使用が可能ですが、効果が現れるまでに時間がかかる場合があります。
受診や治療を迷っている方へ
自律神経の乱れは、放置するとさらに深刻な症状を引き起こす可能性があります。身体の不調や心の不安を感じたら、早めに専門医を受診することをおすすめします。適切な診断と治療を受けることで、自律神経を整え、健康的な日常生活を取り戻す一歩を踏み出せます。
当院では、自律神経の乱れに関する症状のご相談に丁寧に対応し、患者さん一人ひとりに合った治療法をご提案しています。どうぞお気軽にご相談ください。
■自律神経の乱れはどうやって診断(判断)するの?
自律神経の乱れが疑われる場合、自律神経失調症という状態が考えられることがあります。ただし、ICD-10やDSM-5といった国際的な診断基準では、自律神経失調症は正式な疾患名として認められていません。そのため、患者さんの症状や状態を丁寧に伺いながら、類似する疾患を含めて検討し、適切な診断を進めていきます。
自律神経失調症とうつ病の違い
自律神経失調症(自律神経の乱れ)とうつ病には、眠れない、イライラする、倦怠感(疲れやすい)といった共通の症状が見られることがありますが、この二つは異なる疾患です。
自律神経に関連する症状には、うつ病でも現れる場合があります。ただし、うつ病では『うまくいかない』『もうだめだ…』といった悲観的な考えや焦りが強く、日常生活に集中できなくなる状況が続き、長期間ふさぎ込むことが特徴的です。一方、自律神経の乱れでは感情の起伏が大きくなりやすい傾向が見られます。このように、どちらの状態でも症状が似ているため、専門家であっても判断が難しいことがあります。いずれの場合でも、早めに専門家に相談し、適切な治療を受けることが大切です。
自律神経の乱れはどうしたら治りますか(治療方法)?
自律神経の乱れが見られる場合には、症状や原因に合わせて薬物療法や心理療法などの治療を進めていきます。また、必要に応じて生活リズムや食生活の見直しを行い、生活改善にも取り組んでいきます。
監修:こころとからだのケアクリニック人形町 院長 益子 雅笛(ますこ みやび)