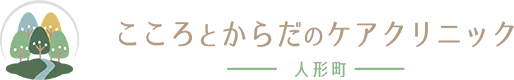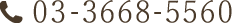若年者に増加している新型うつ病とは?
 職場で叱責を受けた後、会社に行くことや上司に会うことが辛くなってしまい、それが原因で夜に眠れない、朝起きるのが苦しいと感じることはありませんか?一方で、休日にはアクティビティや旅行を楽しんで、その様子をSNSに投稿してしまい、後で同僚からの批判を受けることも。このような状況は、新型うつ病や非定型うつ病の可能性を示しているかもしれません。特に若年層の間でこのタイプのうつ病が増えており、仮病や甘えと誤解されがちですが、実際はうつ病の一形態として認識されています。社会での葛藤や生きづらさを感じている方も多いとされています。
職場で叱責を受けた後、会社に行くことや上司に会うことが辛くなってしまい、それが原因で夜に眠れない、朝起きるのが苦しいと感じることはありませんか?一方で、休日にはアクティビティや旅行を楽しんで、その様子をSNSに投稿してしまい、後で同僚からの批判を受けることも。このような状況は、新型うつ病や非定型うつ病の可能性を示しているかもしれません。特に若年層の間でこのタイプのうつ病が増えており、仮病や甘えと誤解されがちですが、実際はうつ病の一形態として認識されています。社会での葛藤や生きづらさを感じている方も多いとされています。新型うつ病とは何か?
うつ病と聞くと、多くの方が長引く憂鬱な気分や活力の低下といった症状を思い浮かべるかもしれません。このような気分の落ち込みは、新型うつ病においても同様に見られます。新型うつ病の患者さんは、特に厳しい状況下で症状が顕著になることが多いです。従来のうつ病と異なり、状態が許せば外出や旅行も可能です。新型うつ病は2010年頃から注目され始め、その症状の変動性や一般的なうつ病のイメージとの違いから、しばしば理解が得られずに怠けていると誤解されがちです。その結果、患者さんは社会的に孤立しやすい状況になることがありますが、適切な治療によっては改善が見込まれます。何か心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。
有病率について
うつ病は、一般的に10〜12人に1人の割合で見られるとされており、決して珍しい病気ではありません。そして、うつ病患者のうち約30〜40%が新型うつ病である可能性が指摘されています。また、新型うつ病は特に女性に多く見られ、年齢層としては20代から30代が多いとされています。
症状
- 気分が落ち込んでいるが、好きな活動中は気分が一時的に改善する
- 強い倦怠感を感じ、手足が非常に重いと感じる
- 睡眠をとっても、常に睡眠不足のような感覚に悩まされる
- 甘いものを過剰に摂取し、過食傾向になることがあり、体重が増加することもある
- 夕方になると体調が悪くなる
- 他人の評価に敏感で、些細なコメントでも否定されたと感じることがある
- 例えば、上司に叱責された経験がトラウマとなり、上司の顔を見るだけでその嫌な記憶がフラッシュバックする
従来のうつ病と異なり、新型うつ病では好きな活動を行ったり、ストレスの少ない環境下では喜びや楽しみを感じることができます。そのため、外部の人から見ると、病気でないように見えることがあり、活動している際は元気そうに見えるため、健康だと誤解されることがあります。しかし、新型うつ病における気分の落ち込みや大きなストレスへの反応は、従来のうつ病と同様に苦痛を伴います。この状態が社会生活や日常生活に支障をきたすため、医療的介入が必要です。新型うつ病の患者さんが直面する困難の一つとして、周囲からの理解が得られにくいことが挙げられます。これらの問題に対処するためにも、まずは医療機関を受診することが重要です。
原因
新型うつ病は、前頭葉の機能不全が関与していると考えられています。この状態では、感情や情動を管理し、記憶に関与する海馬の機能をコントロールする前頭葉の活動が低下することがあります。これが原因で、感情のコントロールが困難となり、他人の感情や細かな言動に過敏に反応してしまうことが多く、持続的な不安や憂鬱な気持ちが引き起こされると言われています。また、眠気やだるさ、過眠症状も前頭葉の機能低下によって引き起こされるとされています。
診断と治療
新型うつ病は、仮病や甘えだと誤解されがちですが、従来のうつ病と同様に適切な治療が必要な疾患です。
この病気の診断は医師の精密な診察に基づいて行われます。治療には薬物療法が主に用いられるものの、定期的な通院を継続し、通院中に生活習慣の見直しを行ったり、デイケアのような治療プログラムに参加することもお勧めです。これにより、薬物治療と心理社会的治療を組み合わせることで、徐々に改善が見込めます。問題を一人で抱え込まず、ぜひ当院にご相談ください。
新型うつ病への対応
新型うつ病の患者さんは、周囲の言葉や態度に非常に敏感に反応する傾向があります。そのため、他人の発言を被害的に受け取り、「自分が悪いのではなく周囲が悪い」と感じやすく、時には攻撃的な態度をとることがあります。
急性期の対応
新型うつ病の急性期には、従来型うつ病と同様、話に耳を傾け、理解しようとする姿勢が重要です。この時期には、無理をさせず保護的に接することで、安心感を得られるよう努めることが大切です。しかし、このような対応を長期間続けると、新型うつ病の患者さんがその状態に安住し、前に進むための行動が停滞してしまう場合があります。
これは、新型うつ病の患者さんに現実逃避の傾向が強いことが背景にあります。そのため、急性期を過ぎた後の対応には工夫が必要です。
自立を促すための対応
急性期を過ぎたら、患者さんが自立に向けて少しずつ前進できるようサポートしていくことが大切です。以下の対応が効果的とされています
- 適度な心理的距離を保つ:過度に保護的になりすぎず、適切な距離感を意識します。
- 自分自身でできることを任せる:少しずつ責任を持たせ、達成感を得られる機会を作ります。
- 成功体験を評価する:小さな成功を重ねた際には、その努力を認め、適切にほめることで自信を育てます。
こうしたアプローチにより、現実的な行動を取る意欲が湧き、自立への一歩を踏み出す力を養うことができます。
避けるべき対応
逆に、以下のような対応は拒否反応を招き、事態を悪化させる可能性があるため注意が必要です:
- 命令的な言い方:一方的で高圧的な指示は、反発を招きやすいです。
- 否定的な指摘:マイナス面を強調する言動は、自己否定感を強め、状況を悪化させる原因となります。
就業規則や組織としての対応
もし遅刻や欠勤、その他の問題行動が繰り返される場合には、感情的な指摘ではなく、会社の就業規則などに基づいて客観的かつ冷静に対応することが求められます。その際、組織として一貫性のある対応を取ることで、言動に矛盾が生じるのを防ぎ、信頼関係を保つことが可能です。